【贈与・相続】自分用メモの記事に追記しようかと思ったのですが長くなり過ぎるので新記事で書きリンクを貼ることにします。
法定相続人でない第三者が故人の財産を取得することはほとんどないと思います。ただお世話になった第三者に財産をを残したいと考える人も少なくないのかもしれません。
今回は以下の2点を確認しました。
・生命保険の被保険者A、保険料の負担者A、保険金受取人B(第三者)の場合の税金
・公正証書遺言書で指定された人物が第三者の場合の税金
結論から言うとどちらも「相続税」になります。
生命保険の被保険者A、保険料の負担者A、保険金受取人B(第三者)の場合の税金
死亡保険金の課税関係表が国税庁サイトにありました。
出典:国税庁(死亡保険金を受け取ったとき)
被保険者、保険料の負担者、保険金受取人が誰であるかによって税種別は変わります。
生命保険の被保険者A、保険料の負担者A、保険金受取人B(第三者)の税金は相続税になります。
国税庁のサイトの相続税が課税される場合の所に「相続人以外の者が受取人であるときは遺贈により取得したものとみなされます」とあります。
出典:国税庁(死亡保険金を受け取ったとき)
注意点は法定相続人なら使える生命保険の非課税枠(500万円 × 法定相続人数)は使えないということです。
しかし相続税の基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)は使えます。
もし相続税を納税する場合は2割増しになります。
ただ保険金受取人を第三者にするということがハードル高いですからまずはこことクリアしないといけませんね。
公正証書遺言書で指定された人物が第三者の場合の税金
遺言で財産を誰かに遺すことを「遺贈」といいます。「贈」という文字があるので贈与と勘違いされがちですが財産の移転のきっかけが持ち主の死亡であることから税法では「贈与税」ではなく「相続税」の対象とされています。
注意点は死亡保険金を受け取った時と同様です。
・相続税の基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)は使える
・法定相続人なら使える生命保険の非課税枠(500万円 × 法定相続人数)は使えない
・相続税を納税する場合は2割増しになる
出典:遺言で財産をもらった場合の相続税 相続人以外の人に贈る場合の注意点も解説
法定相続人でない第三者が故人の財産を取得した場合のまとめ
・財産の移転のきっかけが持ち主の死亡の場合は相続税の対象
・相続税の基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)は使える
・法定相続人なら使える生命保険の非課税枠(500万円 × 法定相続人数)は使えない
・相続税を納税する場合は2割増しになる
・死亡保険金受取人を第三者にするのはハードル高し
最後に重大な注意点として実務は異なる可能性があるのでやはり最終的にはその時に確認するしかないですね。







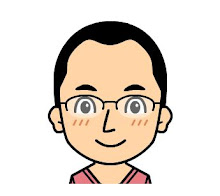
0 件のコメント:
コメントを投稿
お気軽にコメントしてください。