遺言書には公正証書遺言書と自筆証書遺言書があります。
違いは前者の方が「公証人の関与の下、作成されるので信頼性が高い」ということです。
相続財産が多岐にわたったり配分が複雑になると専門家の知識が必要になるでしょう。
しかし私の場合は「自分の財産はすべて配偶者である妻(夫)に相続させる」とする予定なので簡潔なんですよね。
だから自筆証書遺言書でも問題ないと考えています。
自筆証書遺言書を自宅保管しておくと相続時に裁判所の検認が必要になり面倒です。また発見されない、改ざんされるという心配もあります。
そこで自筆証書遺言書保管制度の登場です。
この制度は2020年7月10日からはじまりました。
ここからは「自筆遺言書保管制度のご案内」を参考に自筆遺言書の書き方や相続時の手続きについてみていきます。
参考資料サイト
「エンディングノート 大阪法務局/大阪司法書士会」を作成しました
以下引用及び画像は上記、参考資料のリンク記事より。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
遺言をかいておく意義
公正証書遺言または自筆遺言にしても遺言をかいておく意義は次の2点だと考えています。
◇遺産分割協議より優先される
遺言があれば遺産分割の方法は遺言の内容が優先され、遺産分割協議が不要になる。
ただし次の場合は遺産分割協議が必要になります。
・遺言書に記載されていない財産が見つかった場合
・遺言の内容と異なる内容で遺産分割することに相続人全員が同意した場合
・自筆遺言書で検認を受けていない場合(自筆証書遺言書保管制度を利用した場合は不要)
◇遺言執行者を指定できる
遺言で指定することにより、相続に伴い発生する様々な手続きを執行者が単独で行うことが可能になる。
後者の「遺言執行者を指定できる」は大きなメリットだと考えています。相続人が不仲でなければ問題なく手続きもできるだろうと思いがちですが、おそらく相続時の相続人はそれなりに年老いていると考えられます。
遠方に住んでいたり、認知症になっていたりすると遅々として手続きは進まないでしょう。こういったことを解消できるので「遺言執行者を指定できる」ことは非常に良いことだと感じます。
自筆証書遺言保管制度の特色をPickup
・外形的な確認(全文、日付及び氏名の自書、押印の有無等)
・死亡時通知
遺言者が遺言書を預ける(遺言書の保管の申請)をPickup
・保管の申請ができるのは遺言者の住所地、本籍地、所有する不動産の所在地
・申請に必要なもの
遺言書
保管申請書
本籍と戸籍の筆頭者の記載のある住民票の写し
マイナンバーカード
手数料1通につき3900円
保管申請書とこのようなものです。
保管申請書はありのままを書けばいいので特に難しくはないですね。
遺言書の様式の注意事項をPickup
・「相続させる」と記載
・遺言執行者を記載
・財産目録以外は全て自書する必要がある
ここで私の場合に当てはめて書いてみたいと思います。
一応書いてみましたが調べてみると文言については微妙に違っている書き方もありました。
例をあげてみます。
この辺りは形式と内容が間違っていなければ問題ない気がします。
続いて財産目録については別途妻にわかるようにしておけば添付する必要はないと考えています。遺言書と同じ場所にあればわかりやすいですが、変更があるごとに訂正しなければいけませんから手間を考えるとなくてもいいでしょう。
相続人等が遺言書の内容の証明書を取得する(証明書の請求)をPickup
・遺言書情報証明書は、登記や各種手続きに利用することができる。
ここまでの整理と今後の課題
自筆証書遺言書により妻に全財産を、妻を遺言執行者とすることができます。
これにより妻一人で手続きを進めていくことができます。
ただし今後の課題として妻一人で各種手続きの書類をそろえたりするのはかなり大変ではという懸念があります。
税理士、司法書士などの専門家の力を借りるにしても誰を選んでいいのか迷ってしまうかもしれません。それなりの費用もかかりますからね。
そこで多少というかなり費用がかかりますが遺言信託という商品があり、遺言書作成にはじまり相続開始後の手続きまでサポートしてくれるものです。
こちらを契約しておけば相続人(妻など)の負担はかなり軽減されることになります。
まだ時間はあるでしょうから遺言信託を調べてみることにします。
関連記事:【贈与・相続】自分用メモ
最後に参考資料サイトをもう一度書いておきます。
「エンディングノート 大阪法務局/大阪司法書士会」を作成しました














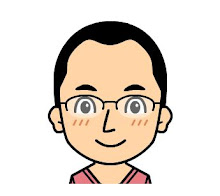
0 件のコメント:
コメントを投稿
お気軽にコメントしてください。